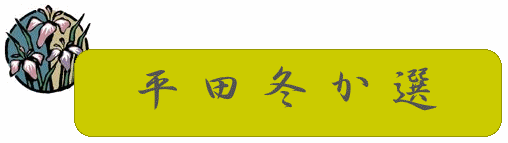 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和8年1月の入選句(兼題:「枯野」、「線虫」)
<特選> 3句
|
| 耳裏を風の触れゆく枯野かな |
太田眞澄 |
| 綿虫の妻葬送の先々に | 野村親信 |
奥様のご葬儀に現れた綿虫です。野辺の送りの先導のように思われたのでしょう。魁(さきがけ)を「先々に」としますと情景としてより伝わるように思います。
| 雪螢橋に漂ふ夕まぐれ |
鈴木寛 |
雪蛍が現れたところが橋で、しかも夕まぐれがというのが情趣があります。語順を入れ替えて下五に「夕まぐれ」とした方が余情が増します。
<その他の入選> 15句
| ひよつとして綿虫天の遣ひとも |
小森葆子 |
ふわふわと漂っている綿虫を見て、ひょっとして天の遣いかも知れないな思った作者の詩情が楽しいです。
| 手のひらに受け雪虫の粘つけり |
小森葆子 |
雪虫の尻につけている白い綿のようなものが少しねばつくようです。手のひらに雪虫を捕らえますと、綿が少し手のひらにつく事からも分かります。
| 綿虫の小刻みに翅震はせる |
太田眞澄 |
綿虫をよく観察されています。小さい綿虫もれっきとした昆虫で透明な羽を頻りに震わせて飛んでいます。焦点を翅の発見にしぼり、「いづこから」という思いは省きます。
| この枯野元浚渫の砂捨て場 |
宮田望月 |
「砂盛る海や」が分かりにくかったですが、浚渫された砂や泥を埋め立てた海が今枯野になっていることかなと思い添削しました。
| これまでを夫と語りつ枯野みち | 鈴木六花 |
枯野みちを歩いている背景から、あれこれ思い出を語り合って歩いている晩年を迎えたご夫婦を思いました。
| 枯野中あれこれ思ふ八十路かな |
鈴木六花 |
辺りの枯野を見て、八十路の自分にひきつけて思いを深くしているのでしょう。語順を替えて調べを整えました。
| 立ち話目の前につと雪婆 | 山崎圭子 |
雪螢は意志があるのか無いのか分からないほどの小さな虫ですので「割って入る」という表現が気になります。立ち話の目の前をつとよぎった位の方が実感に近いと思います。
| 大枯野ここに雑兵供養塚 |
山崎圭子 |
原句のままでも通りますが、大枯野に雑兵の供養塚立てられている事から嘗てこの枯野は古戦場であったことを想像させるというのはどうでしょう。
| 帰ることなき枯野道妻逝けり | 野村親信 |
奥様を失くされている作品ですので「逝く」を遣ってはいかがでしょう。迷ひ込んで帰れなくなったというのでは悲し過ぎます。黄泉路を枯野道に譬え帰る事なきとしてみます。
| 枯野ゆく行けど行けどもなほ枯野 |
深谷美智子 |
| 大枯野行く一両車おもちやめく | 深谷美智子 |
原句でも駄目というのではありませんが平凡です。単線の一両車とそれとなく想像出来そうな読みかたにします。
| 同宿も一人旅らし枯野宿 |
北川和子 |
一人旅の投宿。泊まり合わせた人もまた自分と同じように一人旅の人だったというのでしょう。枯野宿が何だか侘しいですが。
| 同行二人嵐吹く枯野道 |
北川和子 |
「どうぎょうににん」と言う言葉は巡礼をしている遍路を表します。弘法大師がそばに見守ってくれていることを表します。弘法大師に見守られなが嵐の枯野道を札所を目指している姿にしました。
| 限りある命を思ひ枯野行く |
市川毅 |
枯野を歩くことで、自分の晩年というものを再認識することになり、残されたこれからの余生に思いを馳せているのでしょう。
| 綿虫や今日も無言の日となりぬ | 市川毅 |
「綿虫や」で一旦切っているのでその後は綿虫から離れた方がよいです。綿虫に思いを寄せつつ自分の事につい述べてみてはいかがでしょうか。
以上
段戸句会のトップページへもどる